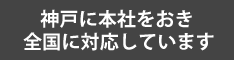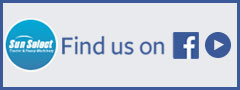目次
農機具には、国税庁が定める耐用年数があります。
耐用年数は買い替えのタイミングの目安となるだけでなく、減価償却費を計算するためにも必要です。
ただし、「農機具の耐用年数はどれくらい?」「耐用年数と減価償却の関係がわからない」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
農機具の耐用年数と減価償却の関係を理解しておかないと、正確な資産価値を把握できず、税務上のリスクがあります。
この記事では、国税庁が定める農機具の耐用年数や減価償却との関係、計算方法などを紹介します。
国税庁が定める農機具の耐用年数

農機具には耐用年数が定められています。ここでは、国税庁が定める耐用年数や寿命との違いについて解説します。
国税庁が定める耐用年数とは
耐用年数とは、建物や機械などの減価償却資産が、通常の使用条件下でその機能を果たすとみなされる期間のことです。
日本では法人税法に基づき、資産の種類や用途に応じて耐用年数が定められています。
なお、法律に基づいている耐用年数は「法定耐用年数」といい、企業が自社の実情や資産の使用状況に基づいて独自に設定する期間を「会計上の耐用年数」といいます。
法定耐用年数は減価償却費を正確に計算し、納税者間の公平性を保つことが目的です。これにより、企業が独自に耐用年数を設定することによる課税の不公正さを避けられます。
一般的には、耐用年数というと法定耐用年数を指します。
農機具の耐用年数は基本的に7年
農機具の耐用年数は基本的に7年です。農機具にはさまざまな種類がありますが、以下の農機具はいずれも耐用年数が7年に設定されています。
- トラクター
- 耕うん機
- 田植機
- コンバイン
- バインダ
- 自走自脱型コンバイン
- 籾すり機
- 米選機
- 乾燥機
- 動力散布機
- 動力噴霧機
- 運搬車
- 刈払機
以前は農機具の種類によって耐用年数が異なっていましたが、平成20年度の税制改正によって7年に統一されました。
農機具の耐用年数が種類に関係なく同じになったこと、耐用年数の管理が不要となり、農業経営者の事務負担が軽減されます。
耐用年数が7年ではない農機具
法改正によってほとんどの農機具の耐用年数が7年になっているものの、以下の農機具の耐用年数は異なります。
- 歩行型除雪機:10年
- 精米機:5年
- 乾燥用バーナー:5年
一部の農機具は耐用年数が7年ではないため、農機具を取り扱う際には事前に確認しておきましょう。
また、同じものでも用途によって耐用年数が異なるケースもあります。例えば、農薬散布用のドローンは耐用年数が7年ですが、宅配サービス用の場合は10年、撮影用の場合は5年です。
耐用年数と寿命は異なる
農機具の耐用年数と実際の寿命は異なる点に注意が必要です。
耐用年数は会計のために使われるものであり、農機具を購入して7年経過したからといって故障するわけではありません。
例えば、農機具のトラクターは一般的に1,000〜3,000時間稼働すると寿命を迎えるといわれています。
仮に2,000時間稼働して寿命を迎える場合、1年間に100時間程度稼働させるなら、10年間は使用可能です。
また、定期的にメンテナンスを行っている場合は、「馬力×100時間」で大まかな寿命年数を計算することもできます。
農機具の耐用年数と減価償却

農機具の耐用年数は、確定申告における減価償却と密接な関係があります。ここでは、減価償却について解説します。
減価償却とは
減価償却とは、事業で使用する固定資産をそれぞれの耐用年数に応じて取得価額を分割し、経費計上する会計処理です。
固定資産には土地や建物、機械設備などがあり、このうち年月の経過によって価値が減少する資産を減価償却資産といいます。
通常、事業に使用する物は経費として計上しますが、一定額を超える減価償却資産は税務上の規定により、購入した年にすべての金額を計上できません。
原則として耐用年数に応じて分割し、経費として計上します。
資産を使用すると機能が低下するため、それに伴い価値が減少し、やがて耐用年数に達すると購入価格に見合う価値がなくなるという考えが減価償却です。
もちろん、耐用年数が過ぎていても寿命を迎えていなければ、価値が残る場合もあります。
減価償却を行う理由
減価償却を行う理由の一つに節税が挙げられます。農機具の購入費用を何年にもわたって償却するため、翌年以降も利益を抑えることが可能です。
特にこれから農業を始めようとする場合は、初期費用として農機具の購入費が多くかかり、安定した収入を得られるようになるまでは数年かかることもあります。
仮に減価償却というルールがなく、農機具の購入費を翌年にすべて計上してしまうと、利益が多くなったタイミングで計上できる経費が少なくなるというわけです。
減価償却を行うことによって、利益が増えてきたタイミングでも農機具の購入にかかった一部の費用を経費として計上できるため、税金を抑えられるメリットがあります。
そのため、農機具を購入した場合は適切に減価償却を行い、確定申告を行うことが大切です。
農機具の減価償却が不要なケース
減価償却が不要なケースとして挙げられるのは、10万円未満の農機具を購入した場合です。
10万円未満の固定資産は少額の減価償却資産として扱われるため、購入金額をそのまま経費として計上できます。
また、青色申告で確定申告を行う場合は、30万円未満の農機具をそのまま経費として計上することも可能です。
必ずしも一括で経費計上しなければならないわけではなく、その年の所得が少ない場合は減価償却し、分割して経費を計上することもできます。
農機具の耐用年数と減価償却の計算方法

農機具の耐用年数と減価償却の計算方法には、定率法と定額法があります。ここでは、それぞれの計算方法と農機具が中古の場合の減価償却について解説します。
定率法
定率法とは、未償却金額に対して一定の割合をかけて減価償却費を求める方法です。
未償却金額は確定申告ごとに減少していくため減価償却費は年々少なくなりますが、一定額を下回ると毎年同じ金額になります。
なお、農機具の減価償却費に定率法を用いる場合は、事前に税務署に届け出なければなりません。定率法の計算式は、「未償却残高×定率法の償却率」です。
耐用年数が7年の場合、定率法の償却率は0.33%になります。仮に100万円で農機具を購入した場合、減価償却費は以下の通りです。
- 1年目:100万円×0.33=33万円
- 2年目:(100万円-33万円)×0.33=22万円
- 3年目:(100万円-33万円-22万円)×0.33=14万円
実際の計算には、償却保証額の考慮も必要となるため注意が必要です。
定額法
定額法とは、減価償却資産の金額に一定の割合をかけて減価償却費を求める方法です。
耐用年数が7年の場合、償却率は0.143%になります。定率法に比べると計算方法が簡単で、定率法のように税務署に届け出る必要はありません。
仮に100万円で農機具を購入した場合、減価償却費のイメージは以下の通りです。
- 1年目:100万円×0.143:14万3,000円
- 2年目:100万円×0.143:14万3,000円
- 3年目:100万円×0.143:14万3,000円
耐用年数が最後となる7年目には、利用中の資産であることを示す必要があるため、全額償却を行わずに1円を残します。
農機具が中古の場合の減価償却
中古で購入した農機具については、すでに償却期間の一部が過ぎているため、耐用年数は適用しません。
農機具を使い始めた時点から、使用可能な期間として耐用年数を見積もります。
ただし、実際には中古の農機具の耐用年数を見積もることは難しいため、簡便法と呼ばれる方法で計算を行うのが一般的です。
耐用年数を経過している場合は、耐用年数の20%を耐用年数として、2年未満の場合は2年とします。農機具の耐用年数は7年で「1.4年」となるため、耐用年数は2年として計算します。
一方、法定耐用年数を途中まで経過しているケースについては、耐用年数から経過した年数を引き、その数に経過した年数の20%を足した年数が耐用年数です。
例えば、3年使用した農機具を購入した場合、耐用年数から使用した3年を引いて4年となります。
経過した3年に20%をかけると0.6年であり、残りの耐用年数の4年と合算すると4.6年です。
農機具の実際の耐用年数を延ばすコツ

農機具を長く使い続けるためには、日頃のメンテナンスが重要です。ここでは、農機具の実際の耐用年数を延ばすコツを解説します。
オイル交換を定期的に行う
耕運機やトラクターなどのエンジンオイルを用いる農機具は、オイル交換を定期的に行うことが大切です。
エンジンオイルはエンジン内部の潤滑や冷却など、稼働するために欠かせません。オイル交換をしないままだと、オイルが古くなったり少なくなったりして故障の原因になります。
オイル交換の目安は使用時間に応じて異なります。初回は20〜50時間程度、その後は100〜200時間を目安に交換しましょう。
ただし、農機具によってメーカーが推奨しているオイル交換のタイミングが異なるケースもあるため、取扱説明書も確認しておきましょう。
保管場所に気をつける
農機具の保管場所は、太陽光や雨が直接あたらない場所が望ましいです。
太陽光があたると部品の劣化や機械の性能低下につながり、雨があたるとサビやカビの発生を引き起こします。農機具の保管場所が悪いと、耐用年数に達する前に寿命を迎えてしまう場合もあるため注意しましょう。
保存場所として望ましいのは、シャッター付きの倉庫やガレージ、屋根のある屋内スペースなどが挙げられます。また、屋外での保管が必要な場合は湿気がこもるためブルーシートは避け、通気性に優れている専用のカバーを使用しましょう。
こまめな清掃とグリスアップをする
農機具を使った後に大きな汚れがある場合は、その場で清掃してグリスアップしましょう。
土や泥などを放置したままにしていると、サビが発生したり、農機具の動作に影響が出たりする可能性があります。また、サビの発生を予防し、金属部分の摩耗を防ぐためにはグリスアップも効果的です。
グリスアップは清掃時だけでなく、シーズン後に長期格納する前や水が大量にかかった後にも行いましょう。なお、グリスにはチューブタイプとスプレータイプがあります。
広い面積にはチューブタイプ、細部への使用にはスプレータイプなど、場所に応じて使い分けを行うのがポイントです。
メーカー推奨のセルフメンテナンスをする
メーカーが推奨しているセルフメンテナンスを行うことも、農機具を長く使うためのコツです。
適切なタイミングでメンテナンスを行うことで、エンジン性能の維持や故障率の低下につながります。農機具を最適な状態に保ち、大きな故障のリスクを軽減し、修理費用の抑制にもつながるでしょう。
セルフメンテナンスの方法はメーカーごとに異なるため、農機具の取扱書やメーカーの公式サイトでチェックします。
まとめ
この記事では、国税庁が定める農機具の耐用年数や減価償却について解説しました。
一般的な農機具の耐用年数は7年と定められています。10万円以上の農機具または青色申告の場合だと30万円以上の農機具を購入した場合、耐用年数に合わせて減価償却を行う必要があります。
また、耐用年数=寿命ではなく、適切にメンテナンスを行うと寿命を延ばすことも可能です。
ただし、農機具の耐用年数が7年と短いように、どれだけメンテナンスを行ってもやがて寿命を迎えます。寿命を迎えた農機具については、買取業者に依頼して買い取ってもらうことも可能です。
農機具の買取なら、株式会社サンセレクトジャパンにお任せください。
サンセレクトジャパンは農機具の買取に強みを持つ専門業者で、全国どこでも無料査定を実施しています。海外への輸出も行っており、幅広い販路を持つのも強みです。
さらに動かなくなった農機具や、寿命を迎えた農機具も買取できます。状態によっては高く買取できる場合もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。